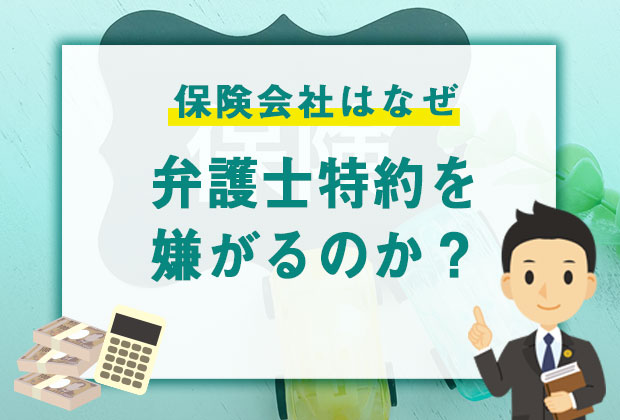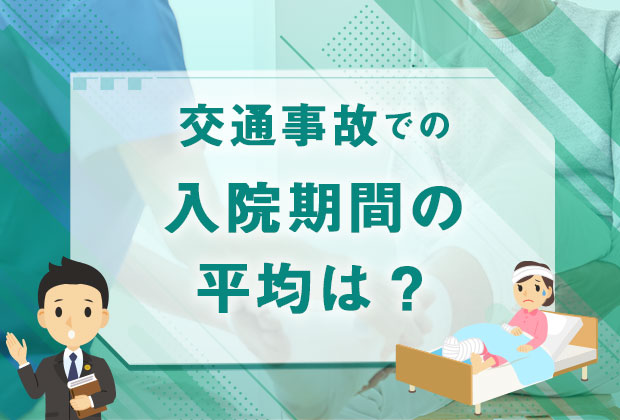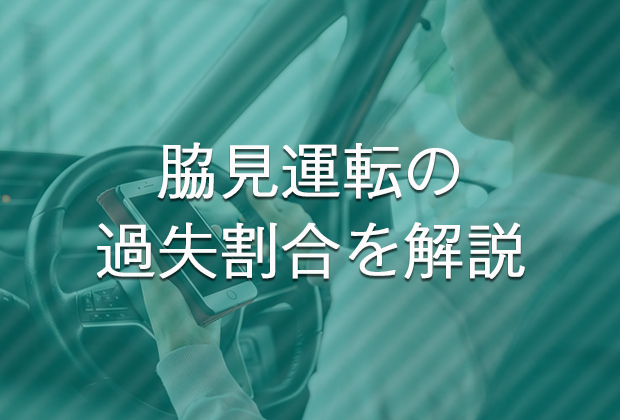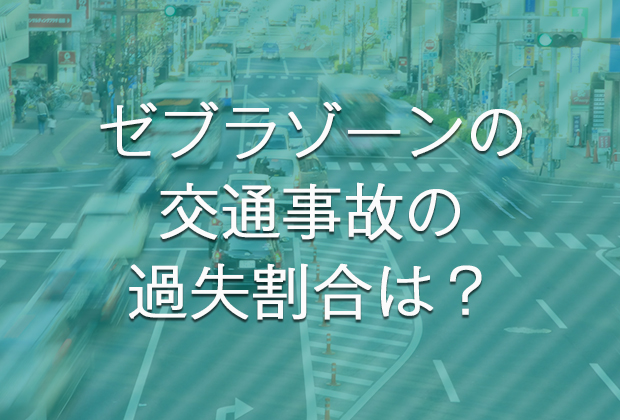交通事故の診断書のもらい方・書き方・提出先を徹底解説
交通事故の被害者となった場合、加害者に対して慰謝料や損害賠償金を求めることになりますが、請求するためには医師から診断書をもらわなければなりません。
診断書は示談交渉だけでなく、警察や勤務先にも提出する必要があるので、事前に用意する診断書の枚数を把握しておくことも大切です。
本記事では、交通事故で診断書を取得しなければならない理由と取得方法、提出時の注意点について解説します。
目次
交通事故の診断書とは?
交通事故の診断書とは、交通事故による怪我や損傷の状態を医師が診断し、その内容をまとめた書類です。
被害者自身が作成するものではなく、医師に依頼して作成してもらう必要があります。
診断書がないと示談交渉で不利になるなどの影響を受ける可能性があるため、交通事故に遭った際は、必ず病院を受診し、診断書の作成を依頼してください。
- 作成年月日:診断書を作成した日付
- 患者情報:氏名、生年月日、住所など
- 傷病名:病気や怪我の名称
- 治療開始日:治療を始めた日
- 治療の内容:行われた処置や今後の
治療予定 - 治癒の見込み:治癒の経過や完治までの
予測期間 - 検査所見:検査結果から導かれる医師の
見解 - 病院名:医師が所属する病院情報
- 医師の署名:診断を行った医師の署名
診断書とは?交通事故で必要になる理由
交通事故の手続きで診断書が必要になるのは、交通事故による被害状況を証明する書類として不可欠だからです。
事故の証明
診断書は、交通事故による怪我を証明するための非常に重要な書類です。
交通事故で怪我を負っても、診断書が無ければ、その怪我が交通事故によるものかどうか判断することができません。
そのため、事故に遭った際には、速やかに病院で診察を受け、医師に診断書の作成を依頼し、交通事故による怪我を正確に記録してもらう必要があります。
慰謝料・損害賠償金の請求
交通事故による怪我の治療費や損害賠償を保険会社に請求する際には、診断書が必要となります。
加害者が任意保険に加入している場合、交通事故による損害は保険会社によって補償されますが、支払われる金額は怪我の程度や治療期間によって異なります。
診断書には怪我の程度や治療内容、予後などが詳細に記載されており、被害者側の主張を裏付けるために欠かせない書類です。
診断書が無いと、示談交渉の場で加害者側から提示される金額が大幅に低くなる可能性があるため、示談交渉を行う前に診断書を取得してください。
労働能力の証明
交通事故によって仕事ができなくなった場合、診断書を用いて労働能力の喪失を証明する必要があります。
労災保険等を請求する際には、怪我の程度や治療期間が詳細に記載された診断書が必要です。
また、長期間の療養を要する場合には、勤務先から復職の時期や労働能力の回復状況を証明する書類として、診断書の提出が求められることがあります。
交通事故の診断書の取得方法
交通事故の診断書は、医師にしか作成できない重要な書類ですので、交通事故が発生した場合は、速やかに病院で診察を受けることが大切です。
医師の診察が遅れると、怪我の状態や因果関係の正確性が低下する可能性がありますので、怪我の程度に関係なく、早めに病院を受診してください。
診断書を作成してもらう際には、必要な検査や治療を受けるだけでなく、医師に事故の状況、受傷部位、症状を正確に伝えることが重要です。
なお、診断書の発行には費用がかかる場合がありますが、加害者に非がある事故の場合、加害者が加入する保険会社がその費用を負担するのが一般的です。
交通事故の診断書は何枚必要?
種類別に解説
交通事故の診断書は、慰謝料・損害賠償金を請求する目的だけでなく、交通事故の内容を証明するための証拠としても用います。
提出する診断書は3種類
交通事故の診断書には、以下の3種類があります。
- 警察に提出する診断書
- 保険会社に提出する診断書
- 後遺障害診断書
警察に提出する診断書は、交通事故を人身事故として扱うために必要な書類です。
診断書を提出しない場合、物損事故として扱われる可能性があり、過失割合でも不利になることがあります。
保険会社に提出する診断書は、治療費などの補償を受けるために必要な書類です。
交通事故の治療費は加害者が加入する任意保険会社から支払われますが、怪我の程度によって補償額が異なるため注意が必要です。
後遺障害診断書は、交通事故による後遺障害等級の認定を受けるために必要な書類です。
後遺障害は、交通事故で受けた怪我の治療後も残存する症状のことをいい、認定を受けるには申請手続きが必要です。
また、症状に応じて後遺障害等級が定められていますので、適切な認定を受けるためには、正確な情報が記載された診断書を提出することが求められます。
提出する分だけ診断書の原本が必要
交通事故の診断書は、提出先ごとに原本の提出が求められることがほとんどですので、提出先の数に応じて診断書を取得する必要があります。
診断書のコピーでは受け付けてもらえない場所もありますし、追加で診断書の作成依頼するのは時間と労力がかかります。
そのため、診断書をもらうときは、事前に必要な枚数を確認してから、医師に発行を依頼してください。
交通事故の診断書はどこに
提出するのか?
診断書の提出先は次の通りで、それぞれの場所に交通事故の診断書の原本を提出することになります。
警察
警察に対しては、交通事故を人身事故として処理してもらうために、診断書の提出が必要です。
人身事故と物損事故では、請求できる慰謝料や損害賠償金の額が異なります。
自動車同士の衝突事故でも、当事者が怪我を負っていない場合、警察は物損事故として処理します。
物損事故として扱われると、交通事故と怪我の因果関係が認められず、加害者に対して治療費を請求できなくなる可能性があります。
そのため、軽度な怪我であっても、交通事故に遭った際には必ず病院を受診し、診断書を警察に提出してください。
加害者側の保険会社
交通事故で負った怪我の治療費等は加害者に支払ってもらうことになりますが、加害者が任意保険に加入しているときは、保険会社が加害者の代わりに治療費等を支払うことになります。
保険会社は、交通事故の状況や怪我の状態などから、慰謝料・損害賠償金の額を算定するため、診断書の提供が求められます。
示談交渉までに診断書を提出できないと、相手方から提示される慰謝料・損害賠償金が低くなるので注意してください。
勤務先
会社で働いている人が交通事故の被害者となった場合、会社に対して休業する連絡をしなければなりません。
休業を認めてもらうためには交通事故で負傷したことを伝える必要があるので、客観的に交通事故の被害状況が確認できる診断書の提出が求められます。
また、勤務中に発生した交通事故の場合には、労災保険が適用される可能性もあるため、交通事故で負傷したときは、勤務先にも診断書を提出してください。
後遺障害等級の認定申請
後遺障害等級の認定申請をする場合、交通事故と後遺症の因果関係があることを証明するために、後遺障害診断書を添付しなければなりません。
後遺障害の申請は加害者の任意保険会社が手続きを行うため(事前認定の場合)、診断書は保険会社に渡すことになります。
被害者が自分で後遺障害等級認定を受けるには、自賠責保険会社に提出することになります。
交通事故の診断書の作成費用
交通事故の診断書の作成費用は、医療機関や診断書の内容によって異なりますが、一般的には2,000円から1万円程度です。
診断書の作成費用は、被害者が一時的に立て替える形になりますが、最終的には加害者側の保険会社から補償を受けられる可能性が高いです。
なお、診断書の費用を請求する際は、証拠として領収書が必要となるので破棄しないよう注意してください。
交通事故の診断書はいつまでに
出せばいい?
必要な補償を受けるためには、提出先ごとに指定されている期限までに診断書を提出することが大切です。
警察
診断書を警察に提出する期限は特に定められていませんが、できるだけ早く提出することが望ましいです。
診断書の提出が遅れた場合、事故と怪我の因果関係が不明確になることで、物損事故として扱われる可能性があるので注意が必要です。
提出時期は事故発生から10日が目安となりますので、事故に遭った際は病院を受診するだけでなく、医師に診断書の作成を依頼してください。
保険会社
保険会社に提出する診断書は、怪我の内容や治療経過などが記載されたものが必要になります。
怪我の状態によって診断書を作成できるタイミングが異なるため、保険会社への提出期限は基本的に設けられていません。
ただし、損害賠償請求権には時効(物損事故:3年、人身事故:5年)があるため、医師に診断書を作成してもらいましたら、速やかに提出してください。
勤務先
勤務先に診断書を提出する場合、就業規則に提出期限の記載があるかを確認してください。
就業規則に提出期限が記載されている場合、その期限までに診断書の提出が求められます。
就業規則に提出期限が記載されていないときは、診断書の提出は任意であるため、提出期限はありません。
ただし、休業等のために診断書の提出が求められることもありますので、事前に総務課などに提出期限を確認してください。
後遺障害等級の認定申請
後遺障害等級の認定申請を行う場合、申請書と一緒に診断書を提出することになります。
後遺障害に関する診断書は、治療しても症状の改善が見込めない「症状固定」の状態にならないと作成してもらえないため、怪我の状態や治療状況によって診断書を提出する時期は異なります。
裁判所
保険会社との間の示談交渉が決裂した場合は、裁判を起こすことになります。
裁判では、当事者双方から提出された資料や証拠のみで事実を認定します。
したがって、被害者としては、どのような怪我をしたのか等を証明するため、裁判所に診断書を提出することになります。
交通事故の診断書は
取り下げることが可能?
人身事故として扱われた場合、加害者は刑事罰や運転免許の停止・取消処分を受ける可能性があるため、それらを回避する目的で診断書の取り下げを求めてくることがあります。
しかし、加害者側から交通事故の診断書を取り下げてほしいという申し出があったとしても、基本的に取り下げることはできません。
診断書は交通事故による怪我等を証明する重要な書類であり、一度医師に作成を依頼した時点で取り下げることは困難です。
なお、診断書に誤りがある場合や訂正が必要なときは、診断書を発行した医療機関に相談してください。
交通事故の手続きで困ったら
弁護士に要相談
交通事故の被害者となった場合、医師に診断書の作成を依頼するだけでなく、さまざまな手続きが必要です。
怪我を抱えながら手続きを進めるのは大変ですし、慰謝料や損害賠償金を請求するためには加害者との示談交渉も行わなければなりません。
加害者が加入している保険会社は、支払う保険金の額を抑えるために、示談交渉を有利に進めようとする傾向があるため、客観的な証拠を提示するなどして対抗することが求められます。
適切な補償を受けるためには専門知識が必須ですので、示談交渉を含む交通事故の手続きについては、弁護士に一任することを検討してください。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠