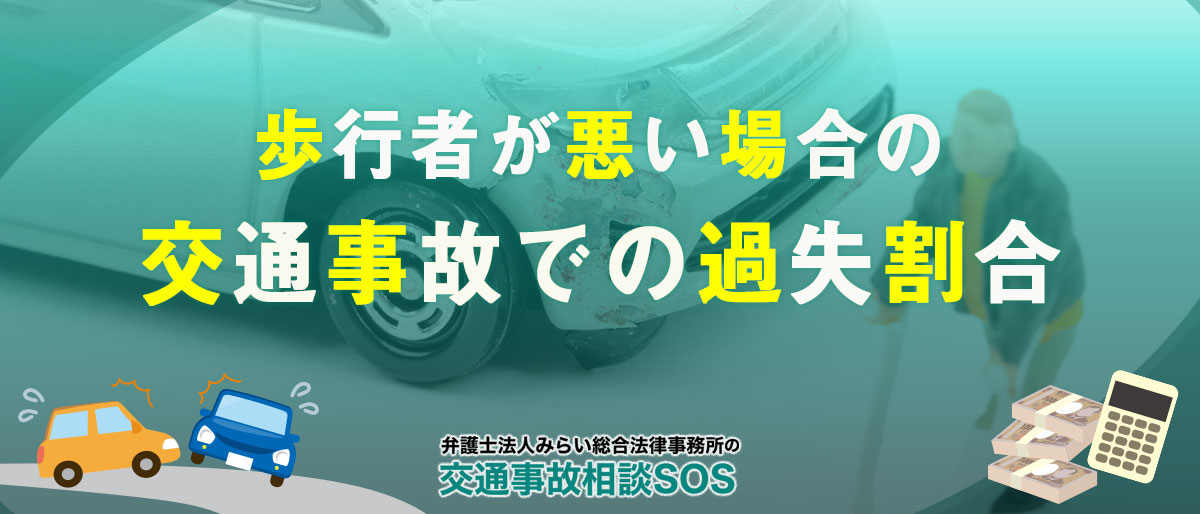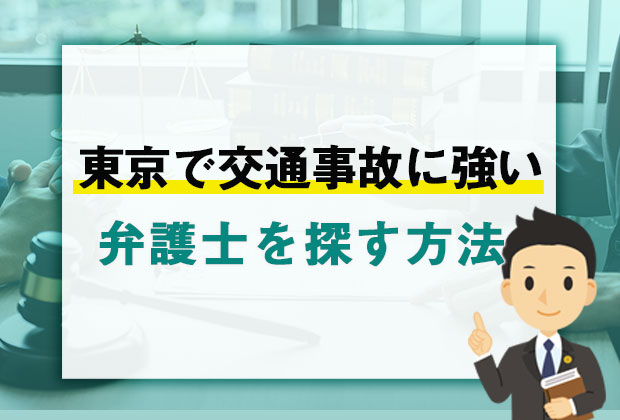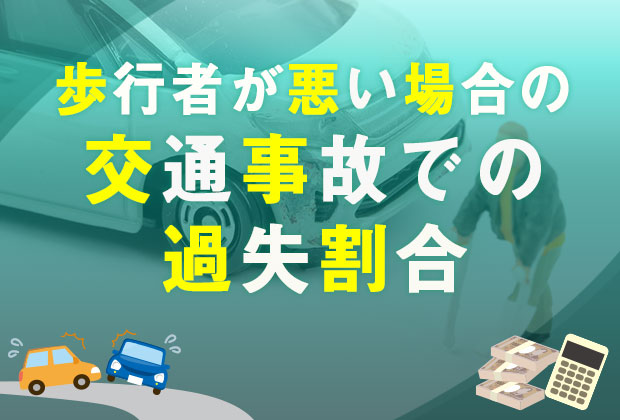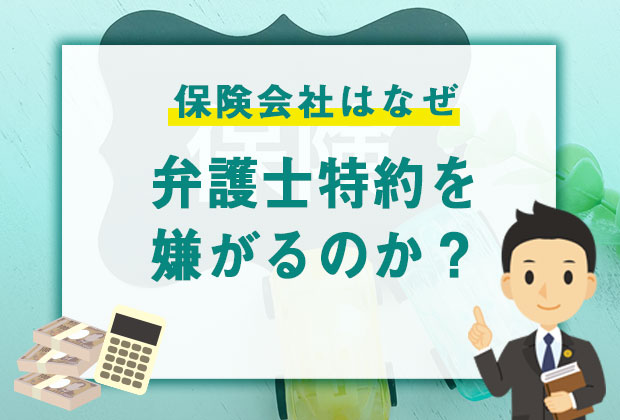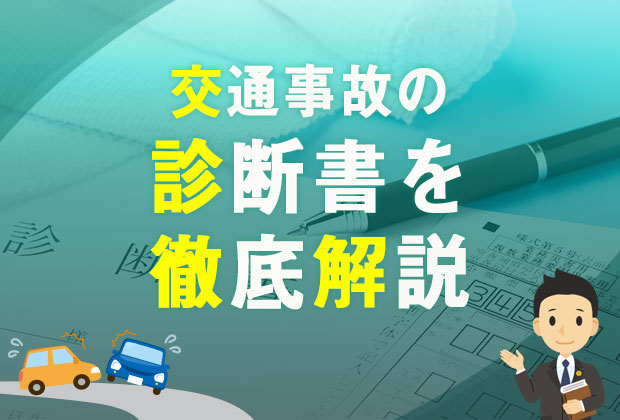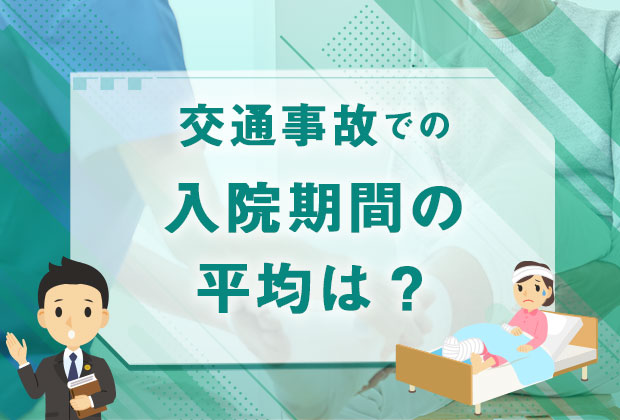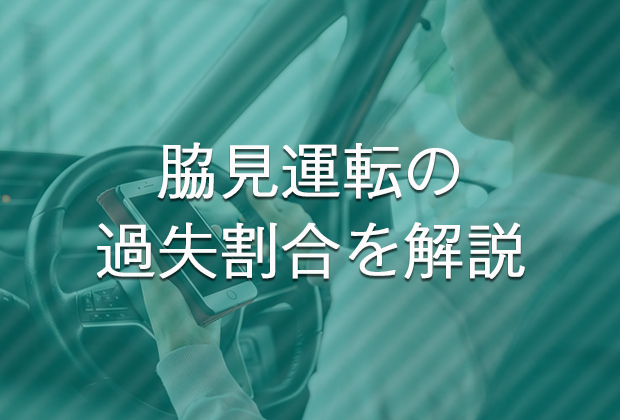車と歩行者の交通事故で歩行者が悪い場合の過失割合。慰謝料はどうなる?
車と歩行者の交通事故では、基本的に車側が事故の責任を問われます。
しかし、歩行者が交通ルールを守らなかった場合には、歩行者にも一定の責任が生じる可能性があるので注意が必要です。
本記事では、歩行者の過失が問われるケースと、車と歩行者の交通事故における過失割合が慰謝料に及ぼす影響について解説します。
目次
歩行者が悪い場合の交通事故とは?
歩行者が交通事故の被害者となった場合でも、次に当てはまる行動をしていたときは、歩行者の過失が問われることになります。
信号無視をして横断歩道を渡る
歩行者が赤信号で横断する行為は、交通事故を誘発する可能性があり、非常に危険です。
車の運転手には、歩行者などに注意を払いつつ安全に運転する義務がありますが、歩行者が信号を無視している場合、運転手が歩行者の動きを予測できず、急停止や回避が間に合わないことも考えられます。
また、夜間や視界が悪い状況では、歩行者側の過失が重くなるので気を付けてください。
道路への急な飛び出し
信号のない交差点や十字路で、歩行者が車の接近を確認せずに飛び出す行動は、主要な交通事故の原因です。
たとえば、12歳以下の子供の交通事故の7割は、飛び出しが原因で発生しています。
大人でも、スマートフォン(スマホ)を操作しながら歩いていたために、道路に出ていることに気付かず、事故が起きることもあります。
通学路や住宅街では、車の運転手も飛び出しに注意しながら運転をしていますが、突発的な行動への対応は難しいため、歩行者が急に道路に飛び出したときは過失が問われることになります。
横断歩道以外の場所を
横断してしまう
横断歩道が設置されているにもかかわらず、歩行者が指定外の場所で道路を横断する行動は、交通事故のリスクを高めます。
たとえば、横断歩道の手前で道路を斜めに横切ったり、横断歩道のない場所で突然反対側の歩道に行こうとするのは危険なだけでなく、事故が発生した際に歩行者側の過失が問われることになります。
高齢者の中には、信号機のある交差点に行くのが面倒だという理由で乱横断する人もいますが、車側が想定しづらい行動は、歩行者側の過失が問われる原因となるので注意が必要です。
交通事故における歩行者の
ケース別の過失割合
交通事故の過失割合は、事故発生時の状況によって変化します。
車と歩行者の交通事故であれば、基本的に車側の過失割合が高くなりますが、歩行者が交通ルールを守っていない場合には、車側よりも過失が重くなることもあります。
歩行者の行動が過失割合に
影響する理由
交通事故における過失割合は、事故の責任を表す数値です。
事故の状況や当事者の行動に基づいて判断されるため、加害者だけでなく、被害者の行動も過失割合に影響を与えます。
たとえば、被害者である歩行者が交通ルールを守っているにもかかわらず交通事故に遭った場合、事故が起きた原因はすべて車の運転手にあるため、過失割合は「歩行者:車=0:10」となります。
一方、歩行者が交通ルールを守らず、車の運転手が歩行者の行動を予見できなかったと認められるケースでは、歩行者側にも交通事故の責任が問われます。
信号機がある場所での歩行者と車の事故の過失割合
信号機がある交差点における交通事故の過失割合は、車が直進している場合と右折(左折)している場合で異なります。
<信号機がある横断歩道の直進車との交通事故の過失割合>
| 信号機の色 (歩行者:直進車) |
過失割合 (歩行者:車) |
|---|---|
| 青:赤 | 0:10 |
| 赤:青 | 7:3 |
| 黄(※):赤 | 1:9 |
| 赤:赤 | 2:8 |
| 赤:黄 | 5:5 |
※青点滅を含む
信号機がある交差点での交通事故の場合、歩行者が交通ルールを守っていれば過失を問われる可能性は低いです。
しかし、赤信号で横断歩道を進んでしまったときは、相手側が車であったとしても、歩行者側の過失を問われることになります。
<信号機がある横断歩道の右左折車との交通事故の過失割合>
| 信号機の色 (歩行者:右左折車) |
過失割合 (歩行者:車) |
|---|---|
| 青:赤 | 0:10 |
| 赤:青 | 5:5 |
| 黄(※):赤 | 1:9 |
| 赤:赤 | 2:8 |
| 青:青 | 0:10 |
| 黄:黄 | 2:8 |
| 赤:黄 | 3:7 |
※青点滅を含む
車が右左折する際に発生した交通事故においても、基本的には車側の過失割合が大きくなります。
歩行者側が青信号、車側が赤信号である場合はもちろんのこと、青信号同士の交通事故においても、基本過失割合は0対10です。
ただし、歩行者が赤信号や、青信号が点滅しているときに横断歩道を渡った際に発生した事故の場合、被害者であったとしても過失を問われるので注意してください。
信号機のない横断歩道の
飛び出し事故の過失割合
信号機のない横断歩道において、歩行者が飛び出したことで車と衝突して発生した交通事故の場合、過失割合は基本的に「歩行者:車=0:10」となります。
車の過失割合が10割になるのは、道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)において、歩行者が横断歩道を進んでいるときは、直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないと規定されているからです。
そのため、歩行者が飛び出した場合でも、車が一時停止しなかったことで事故が起きたときは、車側の責任が問われることになります。
横断歩道が無い場所を歩行者が横断した際の事故の過失割合
歩行者が横断歩道の無い場所を渡ることを乱横断といいますが、乱横断して直進車と衝突した際の過失割合は「歩行者:車=2:8」です。
基本的には車側の責任が重くなりますが、歩行者も横断歩道が無い場所を横断した過失が問われることになります。
信号機がある横断歩道付近を
乱横断した歩行者と車の事故の
過失割合
信号機がある横断歩道ではなく、その付近を歩行者が乱横断した場合、信号機の色で過失割合が変わります。
信号機のない横断歩道は歩行者優先なので、過失割合は基本的に「歩行者:車=0:10」となりますが、乱横断した場所が信号機のある交差点付近のときは、歩行者も過失を問われるので注意してください。
<信号機がある横断歩道付近の歩行者と直進車の交通事故の過失割合>
| 信号機の色 (歩行者:直進車) |
過失割合 (歩行者:車) |
|---|---|
| 青:赤 | 0.5:9.5 |
| 赤:青 | 7:3 |
| 黄(※):赤 | 1.5:8.5 |
| 赤:赤 | 2.5:7.5 |
| 赤:黄 | 5:5 |
※青点滅を含む
<信号機がある横断歩道付近の歩行者と右左折車の交通事故の過失割合>
| 信号機の色 (歩行者:右左折車) |
過失割合 (歩行者:車) |
|---|---|
| 青:赤 | 0.5:9.5 |
| 赤:青 | 7:3 |
| 黄(※):黄 | 3:7 |
| 赤:赤 | 2.5:7.5 |
| 青:青 | 1:9 |
※青点滅を含む
道路交通法第12条(横断の方法)では、歩行者が道路を横断する場合、横断歩道がある場所の付近においては、横断歩道によって道路を横断しなければならないと定められています。
したがって、横断歩道があるにも関わらず乱横断する行為は交通違反となるため、横断歩道を渡った場合よりも歩行者の過失割合が高くなります。
なお、横断歩道付近の範囲は、横断歩道から20m〜30m程度とされていますが、周囲の状況等によって範囲は変動するので注意が必要です。
歩行者の過失割合が加算される修正要素
修正要素は、一般的な交通事故のケース以外に過失割合が変動する要素をいいます。
交通事故が発生した場合には、ベースとなる基本過失割合に修正要素を加えて、最終的な過失割合を算出します。
たとえば、夜間や幹線道路で発生した交通事故においては、歩行者側に5%程度の修正要素が加算されます。
また、歩行者がガードレールを乗り越えて横断しようとした場合や、横断歩道上で立ち止まるなどの行為も、修正要素として過失割合が上乗せされるので注意してください。
歩行者側の過失割合が小さくなる
ケース
車と歩行者の交通事故において、歩行者側の過失が問われるのは交通ルールを守っていないケースなどに限られます。
横断歩道上で青信号を
守っていた場合
歩行者は、交通事故に遭いやすい「交通弱者」に該当するため、車と歩行者の交通事故の場合、基本的には歩行者側が被害者となります。
車同士の事故であれば、被害者が過失を問われることもありますが、歩行者が青信号で横断歩道を渡っているときに車と衝突したケースでは、歩行者が全面的に被害者となるので、過失を問われる可能性は低いです。
法律で歩行者優先が
明示されている場合
信号機が無い横断歩道は歩行者が優先されますので、車の運転手は歩行者の存在に気を付けながら運転しなければなりません。
歩行者が横断歩道を渡っている場合、信号がない横断歩道であっても、車は一時停止が求められますので、そのような場所で交通事故が発生したときも、歩行者の責任が問われる可能性は低いです。
車の運転手に著しい過失・
重過失がある場合
車の運転手に著しい過失や重過失があった場合も、歩行者の過失割合は小さくなります。
著しい過失は、予測可能な危険の無視や注意義務を著しく怠るなど、通常の過失よりも重い責任が問われる行動をいいます。
加害者の著しい過失が原因で交通事故が起きたときは、加害者の責任がより重くなるため、相対的に被害者の過失割合は小さくなります。
- 前方不注意
- わきみ運転
- 運転操作不適切
- 携帯電話の使用
- 酒気帯び運転
- 速度違反(時速15㎞以上30㎞未満)
重過失は、通常の注意義務を著しく逸脱した、極めて重大な過失をいいます。
故意に起こした事故と同程度の扱いがされるため、過失割合だけでなく、慰謝料の額にも影響が及びます。
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 無免許運転
- 正常な運転ができない状態
- 速度違反(時速30㎞以上)
歩行者と車の交通事故で過失割合が10対0になった裁判例
車が歩行者と接触した事故でも、歩行者側に全面的な責任が認められる場合、過失割合が「歩行者:車=10:0」となることがあります。
平成29年12月27日、新潟地方裁判所長岡支部の判決は、歩行者の過失が10割と認定された珍しい事例です。
当時の状況としては、51歳の女性(歩行者)が夜間、片側三車線(道幅約30m)ある国道の中央分離帯を横断しようとした際に車と衝突し、事故が発生しました。
歩行者が乱横断を行った場合でも、通常は車側の過失が問われますが、今回の事故では以下のような要因が考慮されました。
- ・事故現場は街路樹が植えられており、運転手が歩行者を視認することが困難だった
- ・夜間で視界が不良であるだけでなく、対向車線にあるガソリンスタンドの明かりが逆光となり、運転手が歩行者を認識しにくい状況だった
- ・運転手が片側三車線ある中央分離帯を歩行者が横断することを予測するのは難しかった
裁判では、これらの状況を踏まえ、歩行者にすべての過失があると判断され、運転者に損害賠償責任を認めませんでした。
歩行者に全面的な責任があると判断されるケースは非常に珍しいですが、歩行者の行動次第では、本事例のように過失が大きく問われることもあるので注意が必要です。
交通事故の歩行者(被害者)の
慰謝料
交通事故の被害者が請求できる慰謝料には複数の種類があり、その算定方法は任意で選択することが可能です。
慰謝料は3種類ある
交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」・「後遺障害慰謝料」・「死亡慰謝料」があります。
入通院慰謝料は、交通事故の怪我を治療するための入院や通院の費用や、怪我および入通院した精神的苦痛に対する慰謝料をいいます。
治療期間や通院日数が長いほど請求額は大きくなります。
後遺障害慰謝料は、交通事故によって後遺障害を負った際に請求する慰謝料です。
後遺障害は、怪我の治療が終了した後も肉体的・精神的な症状が残る状態をいい、症状に応じて等級が定められます。
重い後遺障害が残ったケースほど、慰謝料の額は高くなりますが、後遺障害慰謝料を請求するためには、認定申請が必要です。
死亡慰謝料は、被害者が亡くなった場合に請求する慰謝料です。
通常、慰謝料は交通事故の被害者に対する補償として行われますが、死亡慰謝料に関しては被害者本人だけでなく、遺族の精神的苦痛に対する慰謝料も含めて請求することになります。
慰謝料の算定基準は3種類
示談交渉では、事故の状況や被害の程度、過失割合などを考慮して慰謝料の金額を決めることになります。
慰謝料を算出する際の基準には、「自賠責基準」・「任意保険基準」・「弁護士基準(裁判基準)」があり、どの基準を用いて慰謝料を計算するかは任意です。
自賠責基準は、交通事故被害者に対する最低限の補償を目的としています。
慰謝料の算定基準の中では最も水準が低く、最低限の補償しかされません。
任意保険基準は、任意保険会社が独自に設定した基準です。
自賠責基準より算定される金額は高いですが、弁護士基準よりは低くなることが多いです。
弁護士基準(裁判基準)は、過去の判例などを基に算定する基準です。
3種類の中で最も高額な補償を期待できる一方、弁護士基準で慰謝料を請求するためには類似する交通事故の裁判例などを確認する作業などを要するため、専門知識が不可欠です。
なお、示談での合意が難しい場合は、調停や裁判などの法的手続きに進むことがありますので、示談交渉で話をまとめたいときは、事前に弁護士に相談してください。
過失割合によって慰謝料は
変動する
被害者の過失が認められた場合、過失相殺によって受け取れる慰謝料が減額されます。
過失相殺は、被害者側にも過失がある場合に、加害者が支払う賠償額や慰謝料が被害者の過失割合に応じて減額される仕組みです。
たとえば、被害者に10%の過失が認められるケースでは、請求可能な慰謝料が10%減額されます。
被害者に過失が認められる場合であっても、加害者が飲酒運転などの重大な過失を犯した場合には、加害者の過失割合が高くなるため、相対的に被害者の過失割合は低くなることがあります。
一方、被害者が信号無視やガードレールを乗り越えて乱横断するなど、交通ルールを守らなかったことが原因で発生した事故では、被害者の過失が通常よりも重くなるので注意が必要です。
被害者も弁護士を付けて
示談交渉すべき
過失割合は示談交渉の場で決めることになるため、被害者も自身の正当性を主張するために弁護士を付けることを推奨します。
適正な慰謝料や賠償額を受け取るためには、弁護士基準で金額を計算しなければなりませんし、加害者から被害者の過失を問われた際には反論する必要があります。
示談交渉において保険会社から提示される金額が正しいとは限りませんので、治療等に専念するためにも、弁護士を付けて交通事故の手続きを行ってください。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠