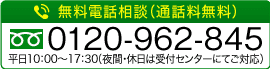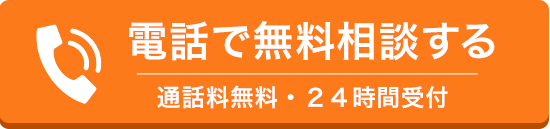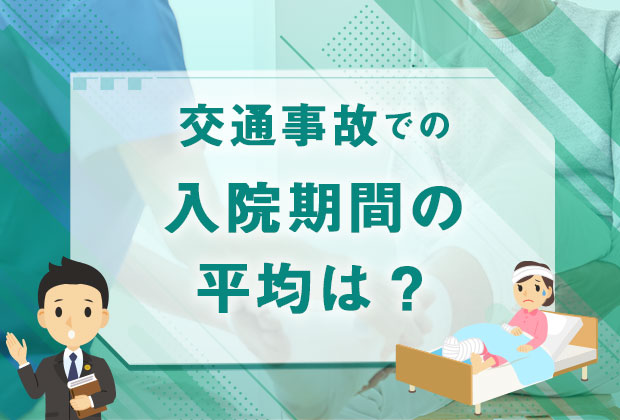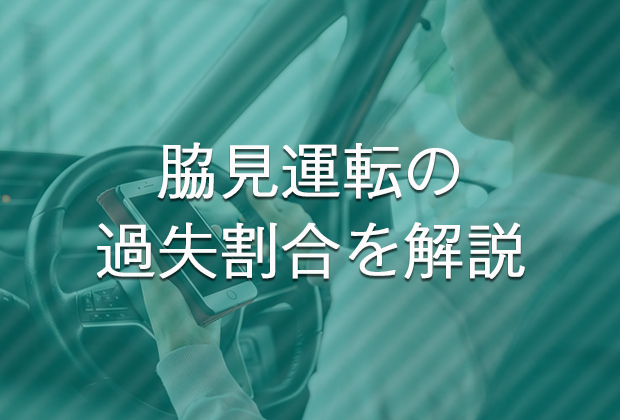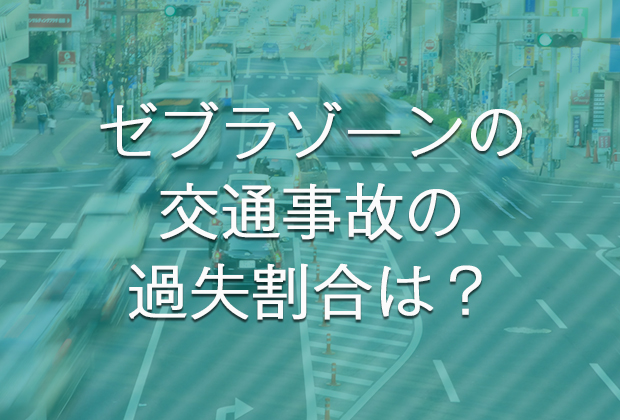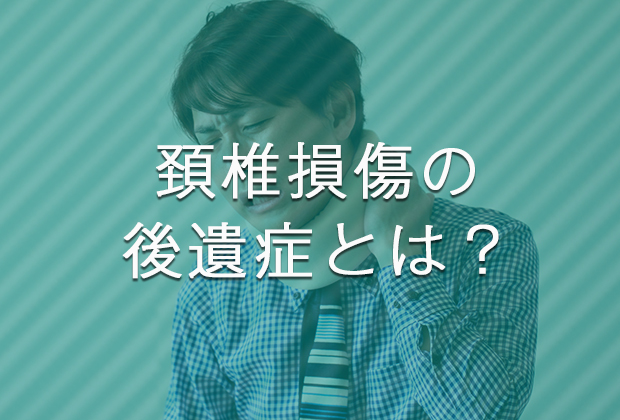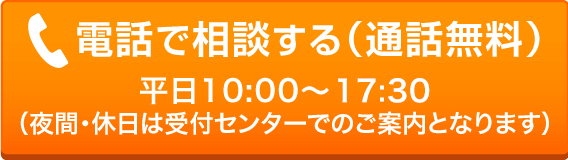交通事故と医療過誤が競合した場合の慰謝料
交通事故と医療過誤
交通事故で被害者を受けた場合には、加害者側に対して慰謝料を請求することができます。
この場合、加害者には、前方不注視などの注意義務違反という過失があるため、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生します。
また、自動車損害賠償保障法により、自動車の運行により利益を受け、また、運行を支配する者(運行供用者)に対しても、損害賠償請求できることになっています。
自賠法は、運行供用者に自賠責保険に加入するよう義務づけていますので、通常は、自賠責保険から賠償金を支払ってもらえます。
さらに、多くの場合には、任意保険にも加入していますので、賠償額の全額が任意保険会社から支払われます。
交通事故でケガをして、治療を受ける場合、適切な医療を受けられればよいのですが、場合によっては適切な医療を受けられず、医療事故が起こる場合があります。いわゆる「医療過誤」の問題です。
医療過誤とは、医療従事者が医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させることを言います。
医師などに善管中義務違反がある場合です。
医療事故があった場合も、被害者はただちに慰謝料を請求できるわけではなく、法律上、損害賠償請求権が発生していることが必要です。
そのためには、医師に故意又は過失があり、行為と結果との関係に因果関係があり、被害者が損害が発生することが必要です。
医師の注意義務について、裁判所は「人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務」(最高裁昭和38年2月16日判決)としています。
共同不法行為
共同不法行為とは
交通事故の態様では、「共同不法行為」ととらえられるものがあります。
たとえば、自動車Aと自動車Bが衝突し、そのはずみで近くを歩行していた被害者Cまで巻き込んでケガをさせてしまった交通事故の場合、AとBの行為によってCに損害が発生しているので、AとBの共同不法行為となります。
共同不法行為の場合、各不法行為者は連帯責任を負います(民法719条)。
先程の例でいえば、交通事故の被害者Cは、A、Bどちらか一方に損害の全額を請求することができます。
AとBの過失割合が異なっていたとしても関係なく、被害者は、たとえ過失割合が低いとしても、より資力のある方に損害賠償額全額の請求をすることができるのです。
ですので、共同不法行為の規定は、被害者保護のための規定といえます。
交通事故の被害者が医療過誤によって亡くなってしまった場合、交通事故加害者と医師の行為が共同不法行為といえるのかが問題となりますが、事故による負傷と医療過誤は、客観的にみても関連した一連の行為であり、その行為と被害者の死亡との間に因果関係もあると認められるため、共同不法行為にあたると考えられます。
共同不法行為を認めた最高裁判決
最高裁平成13年3月13日判決、出典:民集55巻2号328頁です。
この事案は、6歳男子が自転車を運転中、自動車に衝突され、救急車で病院に搬送されたものです。
医師は、一般的な指示をしたのみで被害者を着たくさせたところ、自宅でけいれん様の症状を示し、再度救急車で病院に搬送されたが、頭蓋骨骨折部分の動脈損傷を原因とする急性硬膜外血腫により死亡しました。
最高裁は、被害者は放置すれば死亡するに至る傷害を負ったものの、事故後搬入された被上告人病院において、被害者に対し通常期待されるべき適切な経過観察がされるなどして脳内出血が早期に発見され適切な治療が施されていれば、高度の蓋然性をもって被害者を救命できたということができるから、本件交通事故と本件医療事故とのいずれもが、被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来し、この結果について相当因果関係を有する関係にある、として、本件交通事故における運転行為と本件医療事故における医療行為とは民法719条所定の共同不法行為に当たるとしました。
その上で、加害者と医師との連帯責任については、共同不法行為によって被害者の被った損害は、各不法行為者の行為のいずれとの関係でも相当因果関係に立つものとして、各不法行為者はその全額を負担すべきものであり、各不法行為者が賠償すべき損害額を案分、限定することは連帯関係を免除することとなり、共同不法行為者のいずれからも全額の損害賠償を受けられるとしている民法719条の明文に反し、これにより被害者保護を図る同条の趣旨を没却することとなり、損害の負担について公平の理念に反することとなるとして、責任責任を認めました。
共同不法行為を認めた東京高裁判決
交通事故の加害者と医師の共同不法行為を認めた裁判例に、東京高等裁判所昭和57年2月17日判決(判例時報1038号295頁)があります。
この事案は、交通事故により右下腿開放性骨折の被害を受けた者が片足を切断した件について、「外科医として当然なすべき前記ガスえその発症防止に意を用いることを怠り、感染防止のための創傷の外科的清掃消毒を十分に尽さず、かつ創傷を開放に処置するか少くともガーゼドレナージ等により外界との接触を保つよう処置しなかったのであるから、被控訴人の右下腿開放性骨折に対する医療処置を誤った」として、交通事故の加害者と医師の共同不法行為を認めたものです。
寄与度の問題
交通事故による負傷と医療過誤が共同不法行為だとしても、寄与度による減責を認めるかどうかも問題となります。
寄与度による減責を認めるとは、その結果の発生にどのくらいの責任があったかを判断し、その責任の度合いに応じた損害賠償額だけを支払うことを認めるということです。
たとえば、損害額合計が1000万円として、被害者側が病院に全額の請求をした場合、病院側が、もともとの原因を作ったのは交通事故の加害者であり、レントゲンで異常を見逃したという医師の過失割合は30%であるから、300万円しか支払わない、という主張ができるのか、ということです。
典型的な共同不法行為の場合と異なり、交通事故の負傷と医療過誤は、行為の類型も、行為の時間や場所も異なっていることから、通常の共同不法行為のように連帯責任として一方に全額の支払いを認めるべきではないのではないか、という考えもあるからです。
裁判例でも、交通事故と医療過誤は、時間的前後関係もあり、行為類型も異なるなどの特殊性があることから、各不法行為者は寄与度に応じて損害を賠償することを主張できるとしたものがあります(東京高裁 平成10年4月28日判決)。
この考えによると、交通事故の被害者から損害賠償請求があったとき、裁判所は、各不法行為者の行為の寄与度をそれぞれ認定しなければなりませんが、寄与度の判断は簡単なものではなく、時間も要することになります。
また、寄与度の認定をしたとしても、一方の不法行為者に資力がない場合などは、賠償金の支払いができず、いずれにしても、被害者の救済とは反対の結果になってしまうことが考えられます。
そこで、最高裁判所では、以下のような判決がだされました。
つまり、交通事故による負傷と医療過誤についても、通常の共同不法行為と同様に、不法行為者の寄与度による減責は認めず、被害者はどちらの不法行為者にでも全額の請求をすることができるという立場を最高裁判所がとったということです。
不法行為者間の求償について
被害者からの請求に対し、全額支払ったとしても、自分の負担部分を超えて支払った部分については、不法行為者間で請求することができます。
これを求償といいます。
過失割合については、話し合いでまとまればいいのですが、実際にはもめることが多く、医療過誤の場合は、負傷の程度や、医師の治療内容、経過、結果の予見可能性など、高度で専門的な知識が必要になることが想定されますので、最終的には不法行為者間で、求償の裁判などを起こして、裁判所に判断してもらうことになるでしょう。
【参考論文】
「交通事故と医療過誤の競合事例に関する一考察」石橋秀起著
代表社員 弁護士 谷原誠